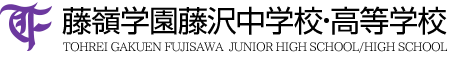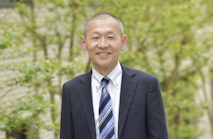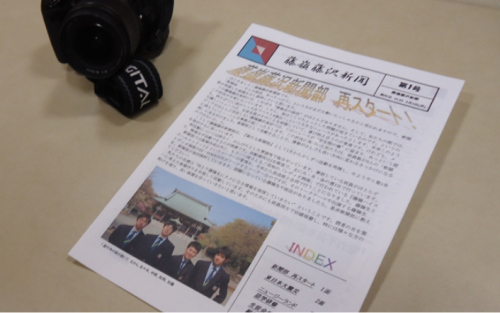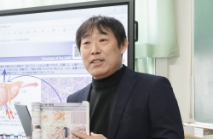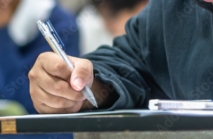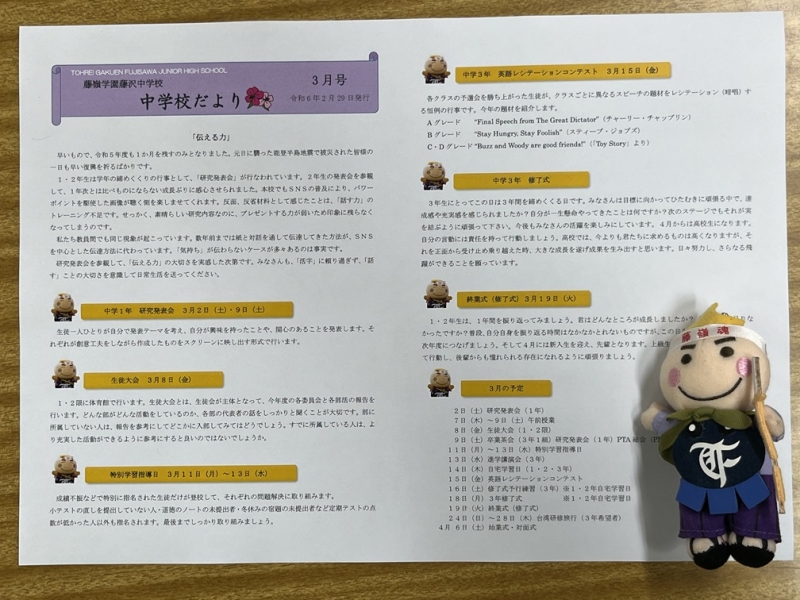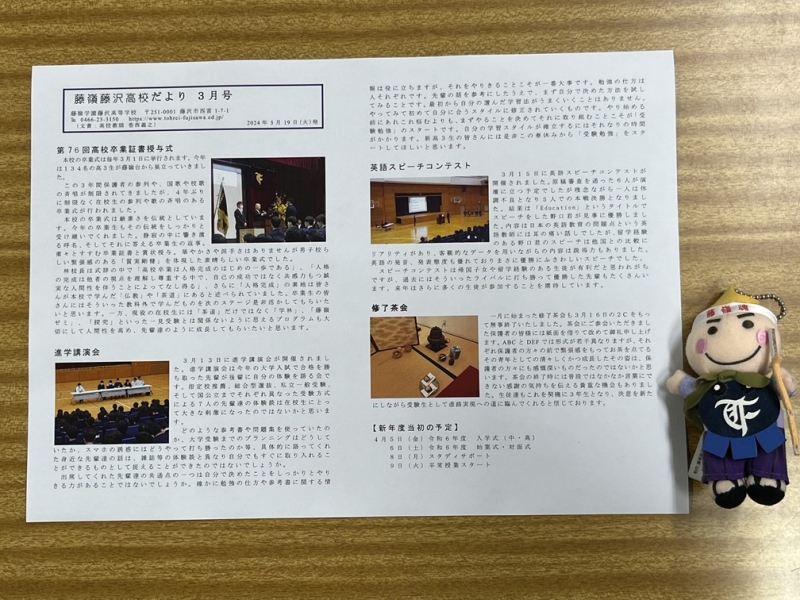「戦死せる紙一片の兄の墓戦後八十年を守り来し」
この歌は、8月18日の「読売歌壇」に掲載されたものです。
今年は「戦後八十年」という大きな節目にあたり、特に八月前半には、太平洋戦争や敗戦、そしてその後の歩みについて考える機会が例年にも増してありました。瓦礫の中から立ち上がった人々の努力が、今日の平和と繁栄を築いたことを忘れてはなりません。同時に、戦争の悲惨さと命の重さを胸に刻むことが大切です。国際情勢はいまも不安定で、世界各地で平和が脅かされています。だからこそ、戦後世代から次の世代へ記憶と教訓をどう受け継ぐかが、今まさに問われているのです。「戦後」とは過去の言葉ではなく、未来を切り拓く責任を私たちに示すものだということを忘れてはなりません。
さて、「棚経(たなぎょう)」をご存じでしょうか。お盆の時期に僧侶が各お檀家を訪問し、先祖の霊を供養する読経を行う行事です。各家では仏壇や精霊棚(盆棚)を整え、位牌や供物を備えます。僧侶の読経とともに家族が手を合わせ、先祖の御霊を迎えて供養するのです。
私も毎年8月11日から15日にかけて「棚経回り」をいたします。軒数は少なくなりましたが、その中には戦死されたご先祖を祀るお仏壇が2件ほどあります。戦死者のお戒名には必ず「院号居士」が用いられ、たとえば「忠烈」といった句が加えられています。また、戦没者には当時の遊行上人から「六字名号」のお軸が授けられており、戦時には仏教界でも「英霊」として手厚く葬っていたことがうかがえます。
遠い外地で戦死された方は、冒頭の歌にある「紙一片」、あるいは「爪」だけが「遺骨」として戻ってきた例も少なくありませんでした。二度とそのような「殉難者」を出さないために、私たちは何をなすべきか――「戦後八十年」という節目は、その問いを私たちに厳しく突きつけています。
この歌は、8月18日の「読売歌壇」に掲載されたものです。
今年は「戦後八十年」という大きな節目にあたり、特に八月前半には、太平洋戦争や敗戦、そしてその後の歩みについて考える機会が例年にも増してありました。瓦礫の中から立ち上がった人々の努力が、今日の平和と繁栄を築いたことを忘れてはなりません。同時に、戦争の悲惨さと命の重さを胸に刻むことが大切です。国際情勢はいまも不安定で、世界各地で平和が脅かされています。だからこそ、戦後世代から次の世代へ記憶と教訓をどう受け継ぐかが、今まさに問われているのです。「戦後」とは過去の言葉ではなく、未来を切り拓く責任を私たちに示すものだということを忘れてはなりません。
さて、「棚経(たなぎょう)」をご存じでしょうか。お盆の時期に僧侶が各お檀家を訪問し、先祖の霊を供養する読経を行う行事です。各家では仏壇や精霊棚(盆棚)を整え、位牌や供物を備えます。僧侶の読経とともに家族が手を合わせ、先祖の御霊を迎えて供養するのです。
私も毎年8月11日から15日にかけて「棚経回り」をいたします。軒数は少なくなりましたが、その中には戦死されたご先祖を祀るお仏壇が2件ほどあります。戦死者のお戒名には必ず「院号居士」が用いられ、たとえば「忠烈」といった句が加えられています。また、戦没者には当時の遊行上人から「六字名号」のお軸が授けられており、戦時には仏教界でも「英霊」として手厚く葬っていたことがうかがえます。
遠い外地で戦死された方は、冒頭の歌にある「紙一片」、あるいは「爪」だけが「遺骨」として戻ってきた例も少なくありませんでした。二度とそのような「殉難者」を出さないために、私たちは何をなすべきか――「戦後八十年」という節目は、その問いを私たちに厳しく突きつけています。